広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻 数理計算理学講座
〒739-8526 東広島市鏡山 1-3-1
Phone & fax. 082-424-7394
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/˜seno/
Email.
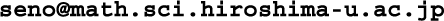
齋藤保久【運営幹事】
静岡大学創造科学技術大学院創造科学技術研究部 ベーシック部門先進科学技術分野
〒432-8011 浜松市城北 3-5-1
Phone & fax. 053-478-1223
Email.
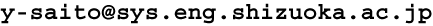
1
目 的
カオスの発見を契機に,生物現象の数理的問題は数学者のみならず幅広い分野に関心を呼んでいます。過去,数学と物理学が相互作用しながら発展してきたよう に,21世紀は生物学上の諸問題を解明するための数学理論及び数理モデルの構築が期待されます。このような時代の背景のもと,生物現象の研究から派生する 数理 的諸問題に対する数学の基礎的研究を発展させ,それを生物現象の研究にfeedbackすることによって,新しい生物学研究数理的研究を促進することが肝 要です。本共同研究では,多様なバックグラウンドをもつ若手研究者と学生が一堂に会し,生物数学の分野における著書や研究論文をベースに,生物現象の特定 の問題 をとりあげ,それについての数理モデルの開発を行います。未解決問題や新たに提起される諸問題の発見・解決を目指して研究交流・討論することにより,生物 数学の研究に刺激を与え るものを発掘すると同時に,生物学の分野における新しい知見の獲得,あるいは,新しい数学的概念の構築を目指します。
2 特 色
2002 年12月17~20日開催の「イッキ読みセミナー(幹事:齋藤保久)」,2003年8月23~28日と2004年5月27~30日開催の 「イッキ読み合宿セミナー(幹事:齋藤保久)」を経て,2004年8月30日~9月3日と2005年8月29日~9月2日には,京都大学数理解析研究所に て 「生物数学イッキ 読み・研究交流(研究代表者:齋藤保久)」が開催され,学術書 「Lecture Notes in Biomathematics "The Golden Age of Theoretical Ecology: 1923--1940"(490頁,Francesco M. Scudo, James R. Ziegler著)」の読破という集会が実現しました。 いずれも,本を読むだけにとどまらず,様々な議論が飛交う場を成し,生物数学の研究に新たに提起される問題の発掘や参加者同士の共同研究が発足するポテン シャルの高いものでした。その肥沃な“土壌”に,今回,生物現象からとりあげた特定の問題に対する数理モデル開発と いう“種” をまく本集会の意義は,多様なバックグラウンドをもつ若手研究者が一堂に会し,共通の問題についての数理モデルの開発や解析に関して討論を展開 するところにあります。研究へのニーズが質的に異なるメンバー間での交流により,議論の活性化はもとより,将来の研究発展と共同研究の可能性を追求しま す。昨今,欧米で盛んに行われ るようになった生物数学関連のスクール形式とはまたひと味違う,出席者参加型の本プロジェクトは学際研究の発展に寄与できる新しい形態であり,本集会の大 きな 特色の一つです。
3 プロジェクト代表者・運営幹事
瀬
野裕美【代表者】
広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻 数理計算理学講座
〒739-8526
東広島市鏡山 1-3-1
Phone & fax. 082-424-7394
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/˜seno/
Email.
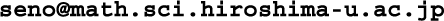
齋藤保久【運営幹事】
静岡大学創造科学技術大学院創造科学技術研究部 ベーシック部門先進科学技術分野
〒432-8011
浜松市城北 3-5-1
Phone & fax. 053-478-1223
Email. 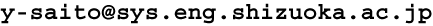
4 募集定員
5 実施内容・日程
本 研究集会では,従来の様式とは少し異なり,参加者には特別講義の内容に関連する文献の集中(“イッ キ読み”) セミナーをしていただきます。参 加者各自が講 義内容を極限まで理解し合うことにより,参加者同士の濃くざっくばらんな研究交流を促し,最前線の話題に潜む新たな問題の“匂い”を嗅ぎ取ろうという試み です。さらに,その後,参加者が数グループに別れ,各グループで最前線の講義と関連するセミナーの内容をシードにして新たな問題の発掘を行い,その問題に 対する数理モデルの 開発および解析に取り組んでいただきます。そして,最終日,各グループの研究成果を発表していただき,コンテスト形式にて審査します(審 査員の審査により優秀グループを表彰します。いわば,ロボコンならぬ“モデコン(モデル・コンテスト)”です。 もちろん,決して,競い合うことを奨励するものではありません)。 それらの研究成果については,京都大学数理解析研究所の講究録としてまとめることを目指します。スケジュールの概要は以下の通 りです:
| 午
前 |
午
後 |
夜 |
||
| 12
月11日(月) |
受
付・説明 |
セッ
ション1 |
セッ
ション2 |
懇
親会 |
| 12
月12日(火) |
セッ
ション3 |
セッ
ション4 |
セッ
ション5 |
|
| 12
月13日(水) |
セッ
ション6 |
懇
談会 |
Group
discussion |
|
| 12
月14日(木) |
Group
pre-presentation/discussion |
Group
discussion |
||
| 12
月15日(金) |
Final
presentation |
Closed
session |
||
■ Final presentation: 本モデルコンテスト。審査員として研究者を招待。
■ Closed session: モデルコンテストの結果発表。優秀グループの表彰。
|
1. 高田壮則 (北海道大・地球環境科学研究院) 「内部構造のある生物集団の数理モデリング — 保全生態学から進化生態学まで」 2. 佐藤一憲 (静岡大・システム工学) 「格子空間上の個体群動態/ぺア近似の数理モデリング」 3. 山村則男 (京都大・生態学研究センター) 「適応戦略を組み込んだ群集動態」 4. 難波利幸 (大阪府立大・大学院理学系研究科) 「種間相互作用と生物群集の数理モデル」 5. 瀬野裕美 (広島大・大学院理学研究科) 「個体群動態離散時間モデルにおける密度効果の数理モデリング」 6. 中島久男 (立命館大・理工学部) 「個体群動態数理モデルから導出される生物群集の全体論的性質」 |
6 参加申し込み
参加申込書を電子メイルにて,運営幹事 齋藤保久(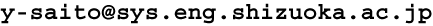 )までお送り下さい。
)までお送り下さい。