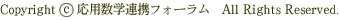![]()
![]()

| 日時 | 2011年6月29日(水) 15:00−17:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階大講義室 |
| 14:50 | 開場 |
|---|---|
| 15:00--15:50 | 小川智久先生 (東北大学大学院生命科学研究科)
◆ 講演題目 真珠の輝きの秘密:タンパク質による真珠アラゴナイト結晶系および配向性の制御 ◆ 内容 生物や生物がつくりだすものの形・模様は、多種多様であるが、 規則正しい構造や美しいパターンを示す。しかし、個体によって 異なるなど、ランダムであり複雑な面も併せもつ。 生物がつくりだすバイオミネラル(硬組織)もその一つである。 真珠貝は、外殻のカルサイトと真珠層であるアラゴナイトの異なる 2種の炭酸カルシウムの結晶系をみごとに作り分けている。 特にアラゴナイト結晶を規則正しく積み重ねたレンガ構造は、 真珠の美しい光沢にも関係する。 本講演では、マベ真珠のアラゴナイト結晶形成を制御しているタンパク質 について紹介する。最近の研究で、真珠形成に関わる役者(タンパク質) が出そろいつつあるが、どんなストーリーで、どのように振る舞い 劇を完結するのか(真珠となるのか)? まだまだ不明である。 そのため、試験管の中で容易に真珠をつくりだすことはできていないが、 数学(数理的解析)の力を借りれば、それも可能になるかもしれない。 |
| 15:50--16:10 | 自由討論 |
| 16:10--17:00 | 吉田徹彦先生 (東亞合成株式会社先端科学研究所所長、慶應義塾大学先導研究センター)
◆ 講演題目 ペプチド創薬ー細胞膜透過性ペプチドと抗菌ペプチドの観点から ◆ 内容 HIV-1 ウイルス由来の TAT(Trans-Activator of Transcription Protein)、及び ショウジョウバエ由来のANT(Antp43-58 (Penetratin) derived from the homeodomain of the Drosophila melanogaster transcription factor)が細胞膜を 通過し、細胞質内へ移行することが、それぞれ1989年、1991年に報告されて以来、 この様な機能を有するペプチドが数多く発見され、細胞膜透過性ペプチド (Cell Penetrating Peptide:CPP)と総称されるようになりました。その後、CPP をタンパク質,ペプチド、低分子化合物に結合することで、これらの分子を細胞内 へ導入し機能させる技術が開発され,ドラッグデリバリーシステム(Drug Delivery System)をはじめとする様々な分野で研究が進められています。またCPPの多くは抗 菌機能を有しており,抗菌ペプチド(Antimicrobial Peptide:AMP)としての特徴を 兼ね備えています。本ワ−クショップにおいて我々の研究室の最新の成果を交えな がら、CPPとAMPを中心にペプチド創薬への展望を考えたいと思います。 ◆ ポスター用の要旨 「トロイの木馬」であり「魔法の弾丸」にもなり得る細胞膜透過性ペプチドを創薬の観点から概観する。 |
| 日時 | 2011年6月8日(水) 15:00−17:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階大講義室 |
| 概要 | 新しいメンバー紹介の第二段です.推進室メンバーと新たなAMFメンバーの研究紹介です. |
| 14:50 | 開場 |
|---|---|
| 15:00--15:50 | 長谷川 雄央 氏(情報科学研究科・数学連携推進室) ◆ 講演題目 伝播する攻撃に対するネットワークの頑健性 ◆ 概略 WWWやInternet といった複雑なネットワークにおいて、故障や攻撃に対する頑健性は重要なトピックの一つである。 次数分布がべき則を示すscale-free networkは各頂点がランダムに攻撃をうける"ランダム攻撃" に対し非常に頑健である一方、 次数の高い頂点から順に攻撃を受ける"選択的攻撃"に対しては脆弱であることが知られている。 しかし、ネットワークに対する脅威は各頂点をランダムに、あるいは選択的に攻撃するものだけで はない。コンピュータ・ウイルスはしばしばリンクを通じてネットワーク上を伝播する。 この種の攻撃に関する頑健性はほとんど議論されていない。 セミナーではリンクを通じて伝播する攻撃としてSIRモデルを考え、 感染の拡がる条件と攻撃に対するネットワークの頑健性を議論する。 特に、防衛戦略~random/preferentialに選んだ頂点にperfect/leaky vaccineを投与する~を考え、 防衛戦略が伝搬する攻撃の振舞いやネットワークの頑健性に与える効果を検証する。 *プレプリントが公開されています: ″Robustness of networks against propagating attacks under vaccination strategies″ Takehisa Hasegawa and Naoki Masuda http://arxiv.org/abs/1102.4878 |
| 15:50--16:10 | 自由討論 |
| 16:10--17:00 | 前田 昌也 氏(理学研究科・数学専攻) ◆ 講演題目 増大する非局所型非線形項をもつシュレディンガー方程式について ◆ 概略 非局所型非線形項をもつシュレディンガー方程式は低次元のシュレディンガーポアソン方程式 などとして登場する. ここでは解の公式をもつ特別な例を考え, 解の時間大域挙動を観察する. |
| 日時 | 2011年5月12日(木) 14:50−17:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階中講義室 |
| 概要 | 情報科学研究科に新たな組織「数学連携推進室」ができました.AMFは,推進室のメンバーと 共に,より活発な活動を展開していきます.今回は,今後の発展が期待される推進室メンバーの 研究紹介の第一弾です. |
| 14:40 | 開場 |
|---|---|
| 14:50--15:40 | 大舘 陽太 氏(情報科学研究科・数学連携推進室) ◆ 講演題目 Designing low-congestion sparse networks ◆ 概略 災害発生時などに道路交通網が寸断されてしまった際, とりあえず一部の主要道路を修理することで,交通網を復旧する必要がある. これは,あるネットワークから疎なサブネットワークを選ぶ事に対応する. サブネットワークの評価としては,元ネットワークとサブネットワークでの「距離の比」が良く研究されていた. しかし,疎なネットワークでは普段より流量が増えてしまうため, 選ばれたサブネットワークが実際に「使えるか」が確かではない. この問題を解決するために,サブネットワークを「混雑度」で評価し, 低い混雑度を持つ疎なサブネットワーク(特に全域木)を選ぶ問題を研究する. |
| 15:50--16:00 | 自由討論 |
| 16:00--16:50 | 三浦 佳二 氏(情報科学研究科・数学連携推進室) ◆ 講演題目 イベント発生時刻の不規則性 ◆ 概略 地震や神経発火などのイベント発生時刻のデータの特徴づけには, 発生頻度の他に,不規則性の指標を用いることもできる. しかしながら,多くのデータにおいては,イベント発生頻度は非定常 であるため,不規則性を適切に特徴付けることは困難であった. 本講演では,ガンマ過程の発生頻度パラメタがどのように 時間変動しても,不規則性パラメタを正しく推定する最適な方法が, 情報幾何学を用いれば求められることを示す.応用例として,脳信号の解読や,地震予知への適用可能性を議論する. |
大変興味深い講演ばかりで、ぜひ今後も注目していきたいと思います。
講演者の皆様、参加いただいた皆様、ありがとうございました。
| 日時 | 2011年1月24日(月) 13:30−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2011年1月24日(金)に青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催いたしました。 今回のテーマは「生物規範光学材料設計」です。 |
| 13:30-14:15 | 吉岡 伸也 氏(大阪大学) ◆ 講演題目 チョウの翅の微細構造と光学特性 ◆ 概略 いモルフォチョウを代表例として、鮮やかな色を持つチョウは、複雑な微細構造を用いて発色を実現している.鱗粉内部の構造は、光の干渉を引き起こす周期性に加えて不規則な要素を併せ持ち、さらには全く異なる構造が上下に積層したハイブリッドな構造を持つ種類もいる.チョウの微細構造が引き起こす光学現象についていくつかの例を紹介し、生物規範光学材料設計のヒントにしたい。 |
|---|---|
| 14:30-15:15 | 不動寺 浩 氏(物質・材料研究機構 光材料センター) ◆ 講演題目 チューナブル構造色材料 ◆ 概略 コバルトブルー(ルリスズメダイ)やネオンテトラの熱帯魚、イカ、タコある種の生物では構造色が変化することが知られている.また、マンドリル(猿)の頬の色がコラーゲン繊維による構造色で同様に変色することが報告されている.近年、この構造色変化にヒントを得た新材料開発が試みられている。講演者は高品質なオパール結晶薄膜の形成プロセスを開発し、さらに構造色が変化する新材料を設計した.これまでの研究とその応用についてご紹介したい。 |
| 15:30-16:15 | 魚津 吉弘 氏(三菱レイヨン株式会社 横浜先端技術研究所) ◆ 講演題目 蛾の目を模倣したスーパー反射防止フィルムの開発 ◆ 概略 ディスプレイの外光による影響の低減の最も有効な手段が、蛾の目の表面構造を模倣したモスアイ型反射防止フィルムである.このモスアイフィルムを大量に安価に製造することを目的に、アルミナナノホールアレイを用いた連続ロール光インプリントの技術開発を進めている。 |
| 16:30-17:15 | 針山 孝彦 氏(浜松医科大学) ◆ 講演題目 森の宝石−発色の仕組みと輝きの意味 ◆ 概略 甲虫目に属するヤマトタマムシの鞘翅は、高い反射率をもつ.これは、長い年月を経ても色の変化を起こさない翅の表層の構造による発色による.数億年の年月を経て進化をとげた昆虫類の翅の色の仕組みと、昆虫間における信号としての意味について考えたい。 |
今回は、CRESTセミナーとの共催で開催いたしました。参加いただいた皆様、ありがとうございました。
| 日時 | 2011年1月21日(金) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階大講義室 |
| 概要 | 2011年1月21日(金)に青葉山キャンパス・情報科学研究科棟2階大講義室において開催いたしました。 |
| 共催 | CRESTセミナー (研究領域:数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索 「離散幾何学から提案する新物質創成と物質発現の解明」 (代表:小谷元子)) |
| 14:40 | 開場 |
|---|---|
| 15:00-15:50 | Jack Koolen 氏(Department of Mathematics、 POSTECH) ◆ 講演題目 Phylogenetic Combinatorics ◆ 概略 An important problem in biology is the construction of the so-called tree of life. In this tree the relations between the different species is encoded. In phylogenetic combinatorics one tries to construct trees ( and networks) on a set of species. There are several reasons that a tree may not fit the input data, for example there are errors in the data, and some of the evolutional processes do not follow a tree model. In this talk I will discuss several network construction which all produce a outplanar graph. In recent work with Stefan Grunewald and Hanguk Kang we show some obstacles why it is not so easy to give a network construction which allows also for internal vertices to be associated with a species. Such a network would be desirable for the study of viruses for example. |
| 15:50-16:10 | 自由討論 |
| 16:10-17:00 | 樋口 雄介 氏(昭和大学) ◆ 講演題目 Spectral structure of the Laplacian on a covering graph ◆ 概略 有限/無限グラフを対象として、その幾何学的性質とグラフ上の作用素のスペクトルの相関関係については、様々な研究者が様々な方向よりアプローチしている。多様体でのスペクトル幾何の結果を試金石としてその離散版の有無に関する研究が見られる一方で、純粋なる組合せ的/離散的図形としてのグラフの幾何的性質に注目した研究も見られる。本講演では、グラフという図形を"多様体の離散モデル"と意識しながらも、敢えてその関連には目を瞑り、離散独自の性質に重点をおいた切り口での「離散スペクトル幾何」の各種結果の紹介をする。ここには多様体の離散的類似物としては扱えそうにない興味深い性質も多々見られるが、しかし同時に多様体においては潜伏状態の"連続的類似物"もあるとも信じている。また、昨今話題の「金属-絶縁体 遷移」のグラフモデルについても述べてみるつもりである。 |
| 17:00 | 自由討論 |
若手研究者の方々の活発な研究の様子がうかがえ、参加者の興味の高さもうかがえ、大変良いワークショップとなりました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました。
| 日時 | 2010年12月8日(水) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟5階小講義室 |
| テーマ | 複雑ネットワーク研究の最前線! 若手研究者が語る数理解析の展望 |
| 概要 | 2010年12月8日(水)に青葉山キャンパス・情報科学研究科棟5階小講義室において開催いたしました。 |
| 14:40 | 開場 |
|---|---|
| 15:00-15:45 | 井手 勇介 氏(神奈川大学工学部) ◆ 講演題目 しきい値モデルの固有値解析とその応用 ◆ 概略 しきい値モデルは、各頂点にランダムな「重み」を割り当て、「異なる 2頂点はその重みの和がしきい値を超えたときのみ辺で結ばれる」というルールで構築されるランダムな単純グラフである。このモデルは、次数分布がベキ分布に従う(スケールフリー性)場合があるなど、様々な注目すべき性質をもつ.本講演では、しきい値モデルの隣接行列およびラプラシアンの固有値・固有ベクトルの解析とその応用例を紹介する。 |
| 16:00-16:45 | 長谷川 雄央 氏(東京大学大学院情報理工学系研究科) ◆ 講演題目 ユークリッド格子から遠く離れて: Nonamenable GraphとComplex Networkの相転移現象 ◆ 概略 従来、統計物理で用いられてきたユークリッド格子と大きく異なるトポロジーを持つグラフの上で多自由度数理モデルを考えた時、どのような相転移現象が期待されるのか? 本講演ではnonamenable graph、complex networkという二例について、ユークリッド格子系では見られない、新しい型の相転移が起こる様子を紹介する。 |
| 17:00-17:20 | 尾畑 伸明 氏(東北大学大学院情報科学研究科) ◆問題提起 ランダム成長、階層構造、スペクトルモデル |
| 日時 | 2010年11月26日(金)13:30 ~ 11月28日(日)14:30 |
|---|---|
| 場所 | 東北大学理学部キャンパス・化学第4 講義棟 |
| 概要 | 物性物理、バイオインフォマティク、医療、生物、人体、逆問題、流体、材料など、様々な問題に出会い、数学が新たに展開しています。その一端を皆様と探索するためのワークショップを開催しました。 ( |
| 主催 | 東北大学応用数学連携フォーラム、 北海道大学数学連携研究センター |
| 後援 | バイオインフォマティクス学会東北支部 |
| 組織委員 | 尾畑伸明(東北大学)・津田一郎(北海道大学)・中村玄(北海道大学)・西浦廉政(北海道大学)・小谷元子(東北大学) |
| 11月26日(金) | |
|---|---|
| 13:20-13:30 | Opening Remark |
| 13:30-14:20 | 木下 賢吾 氏(東北大学) 遺伝子機能推定のバイオインフォマティクス |
| 14:30-15:00 | 小池 亮太郎 氏(名古屋大学) 蛋白質構造変化の記述法 |
| 15:10-15:40 | 金城 玲 氏(大阪大学) 原子レベルの立体構造を通して見るアミノ酸配列と蛋白質機能の関係 |
| Tea | |
| 16:00-16:30 | 弓削 達郎 氏(東北大学) 非平衡定常状態の線形応答の理論 |
| 16:40-17:30 | 川上 則雄郎 氏(京都大学) 1次元量子系と共形場理論 |
| 11月27日(土) | |
| 10:00-10:50 | 鈴木 貴 氏(大阪大学) 腫瘍診断と成長原理解明に関する数理的方法 |
| 11:00-11:50 | 水藤 寛 氏(岡山大学) 新しいタイプの臨床医療診断を目指した放射線医学と数理科学の協働 |
| Lunch | |
| 13:30-14:20 | 坂上 貴之 氏(北海道大学) 渦・境界相互作用の数理科学 |
| 14:30-15:00 | Yu JIANG 氏(北海道大学) MR Elastography のデータ解析手法 |
| 15:10-15:40 | 児玉 大樹 氏(東京大学) ファットグラフを用いたタンパク質の構造モデル |
| Tea | |
| 16:00-16:30 | 鈴木 香奈子 氏(東北大学) 発癌メカニズムを記述するある反応拡散系の解が見せる空間パターン |
| 16:40-17:30 | 中川 淳一 氏(新日本製鐵株式會社) Cultivating an Interface through Collaborative Research between Engineers in Nippon Steel and Mathematicians in Academia |
| 18:00-20:30 | Party |
| 11月28日(日) | |
| 10:00-10:50 | 高木 周 氏(東京大学) 次世代スパコンによる人体のシミュレーション |
| 11:00-11:50 | 大下 承民 氏(岡山大学) ミクロ相分離における粗大 / 安定化 |
| Lunch | |
| 13:30-14:20 | 高木 泉 氏(東北大学) "Where's the peak?": 極大点の在所を求めて |
| 日時 | 2010年10月20日(水) 15:30−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階・大講義室 |
| テーマ | ネットワーク科学の新パラダイムを求めて「グローカル制御」の展望 |
| 概要 | 2010年10月20日(水)に青葉山キャンパス・情報科学研究科棟大講義室において開催いたしました。 今回は「グローカル制御」という新たな研究に注目しました。 |
| 15:00 | 開場 |
|---|---|
| 15:30-16:15 | 原 辰次 氏(東京大学) ◆ 講演題目 大規模動的ネットワーク系の統一的表現とシステム解析:”グローカル制御”の実現に向けて ◆ 概略 ”グローカル制御”の実現には、大規模動的ネットワーク系に対する新たなシステム理論の確立が不可欠である.本発表では、まずそのようなシステムを統一的に扱うための表現の一つとして提案した「一般化周波数変数を持つ線形システム」を紹介し、安定性やロバスト安定性などのシステム解析の幾つかの結果を応用例を交えて示す。 |
| 16:30-17:15 | 井村 順一 氏(東京工業大学) ◆ 講演題目 大規模複雑動的ネットワーク系の制御のための低次元化 ◆ 概略 大規模複雑ネットワーク系の制御系設計を行うには、その数理モデルを低次元化することが不可欠である.本講演では、発表者のグループで最近開発している2つの低次元化法、すなわち、反応拡散構造に基づく低次元化法と特異摂動法による低次元化法について、それらのポイントを簡単に紹介する。 |
多くの方にご参加いただき、活発な議論が行われ、大変有意義なワークショップになりました。ありがとうございました。
| 日時 | 2010年8月2日(月) 13:20−18:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2010年8月2日(月)に青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催いたしました。今回は、数学、工学、生物学の連携を目指し、今回はその第一回としてバイオミメティクスと自己組織化について考える内容となりました。 |
| 13:20-14:00 | 下村 政嗣 氏(東北大学多元物質科学研究所) ◆ 講演題目 バイオミメティクス研究の新潮流と自己組織化 ◆ 概略 生物の持つ多様な構造と機能を模倣した新しい材料・デバイスの研究開発が、今世紀になって欧米を中心に新しい展開をもたらしている。バイオミメティクス(生物模倣)は、新規なマテリアル・デバイスのデザインのみならず、生産技術の革新をも要求するものであり、自己組織化はその中心的な課題である。自己組織化プロセスによって作製した規則的なナノ・マイクロ構造によるバイオミメティック材料について紹介する。 |
|---|---|
| 14:10-14:50 | 津田 一郎 氏(北海道大学電子科学研究所) ◆ 講演題目 コミュニケーション脳理解に対する数学的試み ◆ 概略 コミュニケーションに必要な脳活動の背後に潜む数学的構造を明らかにするためにはどのようなアプローチが可能かについて概説する。カオス的遍歴による脳波の引き込み・脱引き込み転移、ヘテロ結合力学系、ミルナーアトラクターに代表される中立安定性の意義などが議論の対象になる。 |
| 14:50-15:10 | 自由討論 |
| 15:10-15:50 | 吉田 亮 氏(東京大学大学院工学系研究科) ◆ 講演題目 自励振動ゲル:時空間機能をもつ自己組織化マテリアルとしての高分子ゲル ◆ 概略 種々の自己組織化材料に関する研究が盛んに行われている中で、時空間構造を有する新しい機能性ゲルの設計とその応用展開について紹介する。ゲルの中に散逸構造を作り出すシステムデザインによりユニークな機能を創出する新しい材料設計概念を述べる。 |
| 16:00-16:40 | 上野 智永 氏(東京大学大学院工学系研究科) ◆ 講演題目 ゲルを媒体とした反応拡散系におけるパターン形成 ◆ 概略 線形化学反応をゲル媒体中で生起させると自発的に時空間パターンが形成する。 このような非線形化学反応の一つであるFIS反応を用いて、媒体であるゲルを制御することで得られる定在パターンや動的なパターンについて紹介する。 |
| 日時 | 2010年6月10日(木) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2010年6月10日(木)に青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催いたしました。今回は、数学と医学の連携の必要性を考えるをテーマに開催いたしました。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。多くのご参加をいただき、このテーマの関心の高さを感じました。ぜひ、第2弾へとつなげて参りたいと思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 15:00-15:50 | 西田 有一郎 氏(東北大学・医学系研究科) ◆ 講演題目 次世代シークエンサー入門 ~膨大な塩基配列がもたらす生命情報とその舞台裏~ ◆ 概略 2007年に従来の塩基配列解析装置(シークエンサー)に比べて最大1,000倍近いスループットを持つ画期的な機器が出現した。これらは次世代シークエンサーと総称されており、この機器を利用した塩基配列解析プロジェクトが数多く進められている.現在において急激に膨れあがった塩基配列情報から、どのような生命情報が含まれているかを知るために様々な生物情報学的なアプローチが行われている.そこでヒトDNA塩基配列と医学的な関係に注目し、生命情報を取得するためには基本的にどのような手段がとられているかを紹介する。 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 自由討論 |
| 16:10-17:00 | 木村 芳孝 氏(東北大学・国際高等研究教育機構) ◆ 講演題目 遺伝子ネットワークと非線形微分方程式 ◆ 概略 生物の実験がなぜ曖昧な結果しか出てこないのか、その背景に、初期値やパラメータのわずかな違いで結果が大きく変わる非線形微分方程式のトラジェクトリーの構造があること、また、約1万の遺伝子の織りなす非線形微分方程式の系の大域解をどのように推定できるかなどの問題があることなどを、お話しいただきました。 |
| 17:00- | 自由討論 |
多くの参加者があり、終了後の懇親会まで活発な議論と楽しい交流が続きました。
皆様ありがとうございました。
| 日時 | 2010年1月21日(木) 13:40−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2010年1月21日(木)に青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催いたしました。 今回は、GCOE 物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開連携推進企画「数学と物性物理の対話」との共催です。 |
| 共催 | GCOE 物質階層を紡ぐ科学フロンティアの新展開連携推進企画「数学と物性物理の対話」 |
| 13:40-14:30 | Tomasz Luczak 氏(Adam Mickiewicz University, Poland) ◆ 講演題目 Quantum walks on graphs ◆ 概略 In the talk we describe the standard model of quantum walk on graphs pointing out the differences between the classical random walk on graphs and the quantum one. Then we introduce and study a generalized quantum coin random walk and relate our results to the experiments involving the optical Galton board. |
|---|---|
| 14:30-14:50 | 自由討論 |
| 14:50-15:40 | 佐藤 昌利 氏(東京大学物性研究所) ◆ 講演題目 Non-Abelian Topological Order in s-Wave Superfluids of Ultracold Fermionic Atoms ◆ 概略 冷却原子によるs波超流動状態を使って、非可換統計に従う励起状態を実現する方法を提案する。バルクエッジ対応と呼ばれる一種のindex定理を使い、ギャップレスエッジ状態や渦中のゼロエネルギー状態を議論し、また、これらのゼロエネルギー状態が、マヨラナ条件を満たすことにより、非可換統計が実現されることを示す。 |
| 15:40-16:00 | 自由討論 |
| 16:00-16:50 | 小林 未知数 氏(東京大学大学院総合文化研究科) ◆ 講演題目 ボース・アインシュタイン凝縮体の様々な位相欠陥とトポロジー ◆ 概略 極低温液体ヘリウム、および1995年に実現された冷却原子気体におけるボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)は、マクロな数の粒子が1粒子の量子状態を占有している状態で、原子集団はマクロな波動関数を形成し、マクロな量子力学現象を我々に見せてくれる。特に原子気体BECはその制御性と現象を記述する数学との驚くべき一致により、多くの研究者の注目を引きつけている。 BECの本質はゲージ対称性の破れであり、それに伴って様々な位相欠陥が予言され、また観測されている。位相欠陥はBEC研究における中心的課題の1つであり、その数学はホモトピー理論によって議論される。BECで実現されるまたは実現されると期待されている具体的な位相欠陥は量子渦、スカーミオン、モノポール、絡み目構造、インスタントン、ブージャムなど数多く、そして多彩であり、BECはいわばホモトピー理論を実践する宝庫のようなものである。 本公演ではBECの簡単な説明の後にこれらの位相欠陥と、そして幾つかの興味深いダイナミクスを紹介する。 |
| 16:50- | 自由討論 |
| 18:00- | 懇親会(青葉山キャンパス内を予定) |