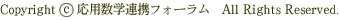![]()
![]()

数学者の参加が多く、活発な意見交換が行われていました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
| 日時 | 12月15日㈫ 13:30−16:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2009年12月15日㈫13:30-16:00 青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催されました。 今回は、CRESTセミナーとの共催で開催いたしました。 |
| 共催 | CRESTセミナー (研究領域:数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索 「離散幾何学から提案する新物質創成と物質発現の解明」 (代表:小谷元子)) |
| 13:30-14:20 | 内藤 久資 氏(名古屋大学多元数理科学研究科) ◆ 講演題目 結晶格子の視覚化と炭素結晶 ◆ 概略 本講演では、Kotani-Sunada による結晶格子の標準実現を3Dコンピュータグラッフィクスを用いて視覚化する手法を紹介する。 また、結晶格子の標準実現の中でも K4 結晶格子と呼ばれる数学的に良い性質を持つものついて、第一原理計算による数値計算の結果にも言及する。 |
|---|---|
| 14:20-14:40 | 自由討論 |
| 14:40-15:30 | 菊池 弘明 氏(北海道大学大学院理学研究院) ◆ 講演題目 単位球上における非線形シュレディンガー方程式の定在波の安定性について ◆ 概略 単位球上の冪剰型非線形項を持つシュレディンガー方程式の定在波の安定性を考える。この方程式は光ファイバー中のレーザービームの伝播等を記述する。 冪の指数をp、空間次元をNとすると、空間領域が全空間の場合は、p = 1+ 4/Nのときは、基底状態は不安定となることがよく知られている。しかし、単位球の場合は、同じ非線形項を考えたとき、基底状態は安定となることがFibich-Merle (2001) により予想されている。 今回は、振動数に適当な条件を課せば、上記のことを証明出来 、さらに、N = 1の場合に限れば、すべての振動数に対して証明出来ることを紹介したい。 講演では、領域が全空間の場合と単位球の場合で異なる現象が起こる原因は何かについて解説したい。 |
| 15:30- | 自由討論 |
活発な意見交換が行われ、大変有意義な会となりました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
| 日時 | 7月28日㈫ 13:30−16:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2009年7月28日㈫13:30-16:00 青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催されました。今回は量子力学の応用に着目して、物理学と化学から講師の先生をお招きして開催されました。 |
| 13:30-14:20 | 平山 祥郎 氏(東北大学理学研究科、ERATO-NSEP) ◆ 講演題目 半導体における量子ホール効果と核スピン制御 ◆ 概略 電荷やスピンを有する粒子がどのように相互作用するかは重要な課題である。意外かもしれないが、このような振る舞いを不純物に邪魔されずに実験できる舞台として現在、最も進んでいるのが半導体量子井戸中の高品質二次元系と強磁場の組み合わせである。 最高水準のAlGaAs/GaAs中では電子は散乱されずに0.1mmも動くことができ、整数量子ホール効果に加えて様々な分数量子ホール効果が観測されている。 分数量子ホール状態をうまく使うと、半導体中で核スピンを 制御することも可能になる。核スピンの制御により、核スピン量子ビットが期待されるだけでなく、高品質半導体でNMR測定が可能になる。 感度の高いNMR測定を用いることで、スカーミオンや傾角スピン状態など、二次元系にユニークなスピン状態が明瞭になってきた。 分数量子ホール効果、高感度NMR、核スピンと電子スピンドメインの相互作用に関しては現在も面白い実験が進行中であり、これらの話題に関して、何が分かったかよりも何が分かっていない かに焦点をあてて話したいと考えている。 |
|---|---|
| 14:20-14:40 | 自由討論 |
| 14:40-15:30 | 保木 邦仁 氏(東北大学理学研究科化学専攻) ◆ 講演題目 第一原理分子動力学法による化学反応のシミュレーション ◆ 概略 本研究では、第一原理分子動力学法を用いてイオン化に伴う分子構造変化の機構解明を目指す。当日は、フェノール—アルゴンクラスターの構造転移およびシクロオクタテトラエンのリング反転・結合交代異性化を例にとり、電子・核の運動を解くことにより、化学結合の消滅・生成に対する知見が深まる様子を示す。 |
| 17:00- | 自由討論 |
ご参加いただきました皆様ありがとうございます。活発な議論が行われ、大成功のワークショップとなりました。今後とも私共の活動にご注目いただければ幸いです。
次回のワークショップへのお越しもお待ちいたしております 。
| 日時 | 5月22日(金) 13:20−18:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2009年5月22日(金) 13:20--18:00 学際科学国際高等研究センター大セミナー室において、第8回ワークショップを開催いたしました。今回は、北海道大学数学連携研究センターと本学GCOE脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点との共催で開催ということもあり、多くの皆様に興味を持っていただき、結果約80人の方々にお越しいただきました。 |
| 共催 | 北海道大学数学連携研究センター、東北大学グローバルCOE「脳神経科学を社会へ還流する教育研究拠点」 |
| 13:00 | 開場 |
|---|---|
| 13:20- | 開会の挨拶 飯島 敏夫 東北大学理事 |
| 13:30-14:00 | 大隅 典子 氏 (東北大学・医学系研究科 / GCOE拠点リーダー) 「数学する脳」 |
| 14:00-14:40 | 郷原 一寿 氏 (北海道大学・工学研究科) 「神経回路のマルチスケールな時空間ダイナミクス -- 理論と実験を接続するプラットホーム構築に向けて --」 |
| 14:40-14:55 | 休憩 |
| 14:55-15:25 | 安田 宗樹 氏 (東北大学・情報科学研究科) 「確率的ニューラルネットワークの相関等式を用いた決定論的学習法」 |
| 15:25-16:05 | 中尾 光之 氏 (東北大学・情報科学研究科) 「階層的生体リズム機構のモデル化」 |
| 16:05-16:20 | 休憩 |
| 16:20-17:00 | 虫明 元 氏 (東北大学・医学系研究科) 「認知的時間と脳」 |
| 17:00-17:10 | 休憩 |
| 17:10-17:50 | 津田 一郎 氏 (北海道大学・電子科学研究所 / 数学連携研究センター長) 「エピソード記憶の神経機構に関する数理モデル:予言と実証」 |
| 17:50- | 閉会の挨拶 井小萩 利明 東北大学国際高等研究教育機構長 |
| 18:15- | 懇親会 青葉記念会館3階レストラン |
お忙しい時期にもかかわらず、ご参加いただきました皆様ありがとうございました。活発な議論が行われ、楽しいワークショップとなりました。
次回のワークショップへのお越しもお待ちいたしております。
| 日時 | 1月16日(金) 15:20−18:00 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科棟2階中講義室 |
| 概要 | 2009年1月16日(金) 15:20--18:00 情報科学研究科棟2階中講義室において、第7回ワークショップを開催いたしました。 |
| 14:50 | 開場 |
|---|---|
| 15:20-16:10 | 片山 統裕 氏 (東北大学情報科学研究科) ◆ 講演題目 ニューロンの細胞内空間における酵素分子の時空間ダイナミクス ◆ 概略 ニューロンの興奮性の調節やシナプス可塑性において重要な役割を担っているC型タンパク質リン酸化酵素(PKC)は、その酵素活性と関連して細胞内局在が変化する性質を有する(トランスロケーション)。 GFP-γPKC融合タンパクを発現させたマウス小脳プルキンエ細胞において、平行線維シナプスの高頻度刺激に伴い、刺激部位近傍から樹状突起に沿ってトランスロケーションが伝播する現象が報告されている。 最近、坪川は、同じ刺激条件で樹状突起内をほぼ同速度で伝播する細胞内Ca2+波が生じることを見出し、これがγPKCトランスロケーション波をリードしている可能性を指摘した。 本研究では、生理学的・解剖学的知見に基づいたプルキンエ細胞の数理モデルを構築し、Ca2+波の再現を試みた。その結果に基づき、トランスロケーション伝播のメカニズムと機能的意義について考察する。 |
| 16:10-16:30 | 自由討論 |
| 16:30-17:20 | 佐藤 耕世 氏 (東北大学国際高等研究教育機構) ◆ 講演題目 ショウジョウバエの性行動の性差を生み出す脳の仕組み ◆ 概略 雄と雌の行動には様々な点で違いがある。例えば、雄は同種の異性を惹きつけ交尾に導くために、しばしば誇張され儀式化された種に特有の求愛行動を行う。一方、雌は一見したところ受動的ではあるが、求愛してきた雄を拒むか、それとも受容するかを決定するのは雌である。このような行動の違いは、行動を生む器官である脳の性差に根ざしていると考えられる。私たちは脳の性差が行動の性差を生み出す仕組みを解明するために、モデル生物であるキイロショウジョウバエを用いて研究を行ってきた。本セミナーでは、私たちの研究により明らかになってきた、脳の一部の神経細胞の性差が性特異的な行動を生み出すメカニズムの一端を紹介する。 |
| 17:20- | 自由討論 |
多くの皆さまに参加をいただき、ありがとうございました。
| 日時 | 10月22日(水) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2008年10月22日(水)15:00-17:30 青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催されました。 |
| 15:00-15:50 | 東海林 亙 氏 (東北大学加齢医学研究所) ◆ 講演題目 ゼブラフィッシュに見る脊髄運動神経細胞の規則的な配列とその形成機構 ◆ 概略 生物の発生過程では様々な局面で周期的な繰り返しのパターンをみることができる。 例えばヒトに代表される脊椎動物では椎骨が首から腰の高さまで規則的に並び、その椎骨に対応した数の神経根が脊髄から末梢に伸長して分節的な神経支配を行うが、これらは全て発生期の周期的な組織パターンを反映するものである。 本講演では体幹部で最も重要な繰り返し構造である体節の形成と、それに対応して調節をうける神経細胞のパターン形成のしくみをゼブラフィッシュ胚を用いた研究から紹介する。 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 自由討論 |
| 16:10-17:00 | 出口 真次 氏(東北大学大学院医工学研究科・工学研究科) ◆ 講演題目 医工学研究における力学・数学の利用 ◆ 概略 生命・生体現象の中には、「力学」の関与が本質的な役割を果たす ものが多い。例えば、呼吸、すなわち息を吸う場合には肺に空気が 流れ込み、肺が膨らむ、そして肺にて交換された空気を、肋骨の筋 肉の収縮によって外に押し出す。もう一つ例を挙げると、コミュニ ケーションを取るために声を出したいときには、ノドを震わせて、胸を張って音を響かせて、口から音を出す。 前記2文で出てきた、空気の流れ、肺の膨らみ、筋肉の収縮、ノドの震え、音の響き、口 からの音の放射、などはいずれも力学が支配的な現象であり、数式 により表現できる。従って、もし、ここで例に出した呼吸あるいは 発声などに関する何らかの実験的計測を行い、その計測結果の解釈 に力学・数学を適用すれば、実験結果を見ただけでは気づかないか もしれない肺やノドなどの生理状態を知ることができるかもしれな い。 本講演では、このような力学・数学を利用した生体診断手法の 開発に関する医工学研究について紹介する。 |
| 17:00- | 自由討論 |
| 日時 | 8月1日(金) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2008年8月1日15:00-17:30 青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催されました。お忙しい中、多くの皆様にご参加いただき、また、アンケートにもご協力いただきまして、ありがとうございました。今後の活動に活かして参りますので、次回以降の参加もお待ちいたしております。 |
| 15:00-15:50 | 岩崎 俊樹 氏 (東北大学・理学研究科、 ◆ 講演題目 カオスと気象予測 ◆ 概略 「来年(2008年)は気象庁が数値気象予測(数値シミュレーションを利用した気象予測)を開始して50年目に当たる。当初、数値予報結果は予報官にほとんど見向きもされなかったが、今日では、気象予測のための基盤業務となっている。 気象現象の精密な再現のためには、もちろん、数値シミュレーションモデルの不断の改良が不可欠である。併せて、カオス的な振る舞いをする大気の予測可能性を考慮して、観測システムの最適化、高度なデータ同化手法の開発、アンサンブル手法の改善などを図る必要がある。 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 自由討論 |
| 16:10-17:00 | 赤松 隆 氏(東北大学・情報科学研究科、 ◆ 講演題目 交通ネットワーク流の数理:渋滞のない世界は実現できるか? ( ◆ 概略 交通ネットワーク・フローの予測・制御問題は、工学・経済学・ゲーム理論・計算機科学・物理学等々、様々な分野の知見が交錯する場であり、多彩な数学が活用されている。本講演では、まず、交通ネットワーク流記述のための代表的な数理モデルを解説し、次に、情報通信技術の発展に伴い可能性の見えてきた新しい交通流制御(混雑管理)方策を紹介する。 |
| 17:00- | 自由討論 |
34名程の参加者があり、無事に終了いたしました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございます。次回の参加もお待ちいたしております。
| 日時 | 5月30日(金) 15:00−17:30 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス学際科学国際高等研究センター大セミナー室 |
| 概要 | 2008年5月30日15:00-17:30 青葉山キャンパス・学際科学国際高等研究センター大セミナー室において開催されました。 |
| 15:00-15:50 | 中山雅晴 氏 (東北大学病院 メディカルITセンター・循環器内科) ◆ 講演題目 バイオインフォマティクス入門 ◆ 概略 ゲノム、転写産物、蛋白質、代謝経路など膨大な生物情報を網羅的に解析する手法が求められている。そのツールとなるバイオインフォマティクスについて、基本的な概念を説明するとともに、今後臨床医療へと役立てるために何が必要かを考察する。 |
|---|---|
| 15:50-16:10 | 自由討論 |
| 16:10-17:00 | 土谷隆 氏(統計数理研究所、 ◆ 講演題目 凸最適化の情報幾何と多項式時間内点法 ( ◆ 概略 この10年余りのあいだに線形計画問題を拡張した凸錐上の線形計画問題が多項式時間内点法で理論的にも実用的にも効率良く解けるようになり、制御、機械学習、信号処理、統計科学、計算機科学等の諸分野において、モデリングや解析のための強力な手法として研究されている。 本講演では、凸錐上の線形計画問題に対する内点法を、情報幾何という微分幾何的な立場から論じ、「計算複雑度」という計算の世界の複雑さを「曲率」という図形の複雑さと定量的に結び付けることを試みる。「モデリング・数理・アルゴリズム」の世界が互いにさまざまな形でかかわりあっていることを伝えたい。 |
| 17:00- | 自由討論 |
雨模様の中、多くの方にご参加いただき、お蔭様で無事に終了しました。
| 日時 | 3月14日(金) 13:00−15:45 |
|---|---|
| 場所 | 青葉山キャンパス情報科学研究科2階中講義室 |
| 概要 | 2008年3月14日13:00-15:45 青葉山キャンパス情報科学研究科2階中講義室にて開催されました。この度、応用数学連携フォーラムは国際高等融合領域研究所内に事務局を設置することとなりました。それを記念して、はじめに国際高等研究教育院 井原聰院長からご挨拶をいただきました。 |
| 日時 | 11月22日(木) 15:00-18:00 |
|---|---|
| 場所 | マルチメディア教育研究棟6F大ホール左側 (川内北キャンパスマップはこちらをご覧ください) |
| 概要 | 2007年11月22日15:00-18:00 マルチメディア教育研究棟6F大ホールにて開催されました。近日公開予定の応用数学相談窓口掲示板のデモが行われました。お蔭様で無事に終了しました。 |
| 15:00 | 開場 |
|---|---|
| 15:10-16:00 | 高木泉(理学研究科数学専攻) 「隠喩(メタファー)から模型(モデル)へ」 ◆ 概要 ヒドラの再生実験のモデルを例にとって、基本原理がはっきりしない複雑な生命現象を扱う上で数理的方法がどうような役割を果たし得る かを考察する。 |
| 16:00-16:20 | 自由討論 |
| 16:30-17:20 | 大林茂(流体科学研究所) 「流体設計と数理モデル ~家電製品から航空機まで~」 ◆ 講演題目 掃除機から航空機まで、「ながれ」を利用した製品は至る所に存在する。 「ながれ」のシミュレーションと設計で用いられている数理モデルについて紹介する。 |
| 17:20- | 自由討論 |
お蔭様で無事に終了しました。
応用数学連携フォーラム発足記念として開催いたしましたところ、50名以上の参加者を集めて盛会のうちに終わりました。講演してくださった方々、質問やコメントをお寄せいただいた方々をはじめ、熱心に聴講してくださったすべての皆様に感謝いたします。
ワークショップを通して、応用数学への関心の高さ、異分野への旺盛な好奇心、研究交流に対する要望や熱意をひしひしと感じました。そして、講演者の皆さんがとても楽しそうに話をされるのに触れ、前向きな元気がますます沸いてきたという方も多かったのではないでしょうか。
応用数学連携フォーラムでは、分野横断的に多くの方々がつながるネットワークとなり、新しい交流から新しい着想が共同研究に育ってゆくことを願っています。そのための小さな第一歩を踏み出したところです。多くの方々のご参加を心からお待ちしています。
| 日時 | 2007年9月4日13:00-18:00 |
|---|---|
| 場所 | 情報科学研究科中講義室 |
| 講演資料 | 徳山 豪 「ディジタル星型領域とディスクレパンシー -- 富士山を認識するための数学」 宗政昭弘 「球面上の最適配置入門」 |
| 概要 | 応用数学連携フォーラム発足記念として開催いたしましたところ、50名以上の参加者を集めて盛会のうちに終わりました。 |